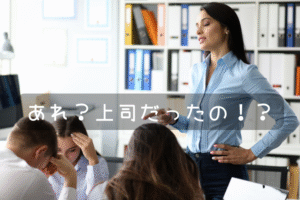若手管理職必見!外国人部下の能力を最大限に引き出す声かけ術

こんな悩みを抱えていませんか?外国人部下の評価が一致しない理由
評判と実力が一致しない場面とは?
他部署で高く評価されていた外国人部下が、新しい環境では思ったほど力を発揮できない場面は決してめずらしくない。
それは、能力の問題ではなく「環境や関係性のちがい」が大きく影響していることが多い。
たとえば、前の部署では同じ国の同僚が多くいたり、上司が英語でのコミュニケーションに慣れていたりすることで、本人が安心して力を出せていた場合がある。
それに比べて、今の職場では日本語でのやりとりが中心だったり、意思疎通のテンポが違ったりして、持っている力をうまく出せないというケースも多い。
また、「プロジェクトにかける期待」が大きいほど、周囲の視線も厳しくなり、ちょっとしたミスや言葉のずれも目立ちやすくなる。
能力を疑う前に、「前の環境とは何がちがうのか」に目を向けることで、問題の本質が見えてくることがある。
本人の持っている力が消えたわけではなく、引き出し方が変わっただけと考えることが大切である。
能力を発揮できない3つの背景
外国人部下が前の部署ほどの力を出せない背景には、いくつかの要因がかさなっている。
その中でも大きな影響をあたえるのが
- 「言葉や文化のちがい」
- 「職場の空気感」
- 「本人の気持ち」
である。
たとえば、言葉のニュアンスが伝わらなかったり、日本独特の“空気を読む”感覚に戸惑ったりすると、本人が思っている以上に消極的になってしまうことがある。
また、職場の雰囲気がこれまでとちがうだけで、自分が歓迎されていないように感じてしまうこともある。
さらに、周囲の期待が高いことで「失敗できない」と自分にプレッシャーをかけてしまい、結果として慎重になりすぎてしまう場面も少なくない。
力を発揮できないのは、能力の問題ではなく、今の状況に心や体がなじみきれていないことが原因である可能性がある。
これらの背景を知ることは、部下を理解し、支えるための大きな一歩になる。
言語や文化の壁
言葉や文化のちがいは、思っているよりも日常の行動や気持ちに影響をあたえる。
とくに、日本語の微妙な言い回しや「察する」文化は、外国人部下にとっては高いハードルとなることが多い。
たとえば、何かをたのむときに「〜してくれると助かるな」と伝えた場合、こちらがやんわりお願いしているつもりでも、相手には「別に強制ではない」と受けとられてしまうことがある。
また、日本の会議でよく見られる「沈黙の時間」や、あいまいな表現が、意見を言うタイミングをむずかしくさせる場合もある。
このような言語や文化のちがいを前提として理解しておくことで、「なぜ伝わらないのか」と感じる場面が減り、より建設的なやりとりができるようになる。
職場環境や人間関係の違い
職場の空気や関係性が変わるだけで、人は思った以上に力を出しにくくなる。
とくに、異動して間もない外国人部下にとっては、新しい人間関係を築くこと自体が大きなストレスになる。
たとえば、前の部署ではおなじ国の同僚がいて、冗談や悩みも共有できる関係があったのに、今はまわりが全員日本人で、気軽に話せる相手がいない。
あるいは、チームの雰囲気が静かであまり声をかけられないために、「話しかけてはいけないのでは」と遠慮してしまうこともある。
環境や人との距離感がちがうだけで、安心感がぐっと減り、自信も行動もゆるやかに弱まっていく。
だからこそ、まずは話しかけやすい空気をつくることが、力を引き出す土台となる。
本人の自己評価や不安
外国人部下が自分に対してプレッシャーを感じすぎてしまうことが、力を出せない大きな理由になることがある。
これは、自信がないというよりも「期待に応えようとしすぎる気持ち」から来ている場合が多い。
たとえば、重要なプロジェクトメンバーとして異動してきたことを、本人は重く受け止めている。
まわりの評価や期待が高いほど、失敗を恐れて動きが慎重になり、いつもならすぐにできることにも時間がかかってしまう。
さらに、自分の日本語力や仕事の理解度に不安があると、「確認したいけど聞きづらい」と感じて、ひとりで抱えこんでしまうこともある。
こうした不安や緊張を少しずつやわらげるには、安心して失敗できる空気や、小さな成功を認める声かけが、心の支えになる。
あなたが感じている「モヤモヤ」の正体
外国人部下の力が発揮されないとき、管理職であるあなたが感じている「モヤモヤ」には、実は明確な理由がある。
それは、「期待と現実のギャップ」にどう向き合えばいいか、まだ見つけられていない不安から生まれている。
たとえば、前部署で高評価だったと聞けば、「すぐに活躍してくれるはず」と思うのは自然なこと。
ところが実際には、説明が伝わっていないように見えたり、積極的な提案が出てこなかったりと、想像とちがう姿に戸惑ってしまう。
「本人のやる気の問題なのか?」「教え方が悪いのか?」と自分を責めたり、逆に相手を評価しなおすべきか悩んだりすることもある。
でも本当のところは、相手の力そのものが足りないわけでも、自分のマネジメントがまちがっているわけでもない。
このモヤモヤの正体は、「文化・言葉・環境」のちがいをどう埋めるか、まだ手がかりが見つかっていないことにある。
気づいてほしいのは、あなたがそのギャップに向き合おうとしている時点で、すでに大切な一歩をふみ出しているということ。
このあと紹介する“声かけ”の工夫が、そのモヤモヤをやわらげ、信頼関係をつくるきっかけになるかもしれない。
解決のカギは“魔法の言葉”にあり!
押し付けにならないコミュニケーションとは
外国人部下との信頼関係を築くには、「指示」ではなく「対話」を意識した声かけが大切である。
押し付けにならないコミュニケーションとは、相手の立場や気持ちをくみとった上で、こちらの思いをやわらかく伝える工夫がされているやりとりのことである。
たとえば、「もっと主体的に動いてほしい」という場面でも、「なんでやらないの?」ではなく、「どうすればやりやすくなるかな?」と問いかけるだけで、相手の感じ方は大きく変わる。
また、「これは〇〇しておいて」と伝えるよりも、「〇〇してもらえるとたすかるな」と話すことで、命令ではなくお願いとして伝えることができる。
大切なのは、相手に考える余白をあたえることである。
「こうすべき」「こうしなさい」と言いきってしまうと、相手は自分の意思を出せなくなってしまう。
対話の中に、相手の意見や思いをくみとる一言をそえることで、自然と気持ちがほぐれていく。
「伝える」よりも「つながる」ことを意識した声かけが、信頼と協力の土台をつくる第一歩となる。
モチベーションが上がる声かけの特徴
外国人部下が安心して力を出せるようになるためには、内容だけでなく「伝え方」に工夫が必要である。
その中でもモチベーションを高める声かけには、いくつか共通する特徴がある。
たとえば、行動の結果だけを評価するのではなく、そこにいたるまでの「取りくむ姿勢」や「考え方」に目を向ける。
さらに、「信頼してまかせる」というメッセージを言葉にして伝えると、相手は自分が必要とされていると感じやすくなる。
そして、文化や価値観のちがいに対しても、否定せずにリスペクトの気持ちを見せることで、心の距離がぐっと縮まる。
本人のやる気を引き出すのは、正しさではなく「気持ちに届くことば」である。
声かけを変えるだけで、部下の目の輝きが変わる瞬間が、きっと見えてくる。
行動ではなく「姿勢」を褒める
部下のやる気を引き出すためには、結果よりも「取りくむ姿勢」に目を向けたほうが効果がある。
とくに外国人部下にとっては、まだ職場のルールや表現になれていない中で努力していること自体が大きな価値になる。
たとえば、「報告書の内容が正しかった」だけでなく、「何度も確認しながら丁寧に仕上げてくれてありがとう」と伝えることで、自分のがんばりがちゃんと見えていたことが伝わる。
また、「まだ完ぺきではないけれど、成長しようとする姿が伝わってきたよ」といった一言は、本人にとって大きな励ましになる。
大切なのは、「うまくできたか」ではなく、「どう向き合ってくれたか」を見ているというメッセージである。
この視点が、相手の心に安心感と自信を届けてくれる。
信頼して任せる言葉
「あなたを信じている」というメッセージは、どんなアドバイスよりも大きな力を持っている。
信頼されていると感じたとき、人は責任と自信をもって行動できるようになる。
たとえば、「これ、お願いしても大丈夫?」ではなく、「あなたならできると思って、お願いしたい」と言われたとき、自分の価値を認められたように感じる。
また、「途中で困ったら一緒に考えるから、まずは任せてみたいな」と言われれば、挑戦しやすくなるし、必要以上にプレッシャーを感じずにすむ。
信頼は一方的に示すのではなく、ことばにして伝えることで、初めて相手の心に届く。
部下が安心して前を向けるようにするには、この「任せる言葉」の力を上手に使うことが大切である。
文化を尊重する姿勢の伝え方
文化のちがいを認めるだけでなく、そこに興味を持ち、尊重する姿勢をことばにして伝えると、信頼関係は大きく深まる。
とくに外国人部下にとっては、自分のバックグラウンドが受け入れられていると感じられることが、心のよりどころになる。
たとえば、「それってあなたの国ではどうするの?」と聞いてみたり、「そういう考え方、おもしろいね」と受けとめたりするだけで、相手は安心して話せるようになる。
また、「日本ではこうだけど、あなたの考えもぜひ聞かせて」と言えば、意見を交わせる空気がうまれやすくなる。
文化のちがいは、壁ではなく、相互理解のチャンスである。
「あなたの文化も大切にしたい」というメッセージは、相手の心に深く残り、行動のモチベーションにつながる。
NGな言葉・態度はこれだ!
外国人部下との関係づくりでつまずきやすいのは、知らず知らずのうちに使ってしまう言葉や態度である。
相手を思ってのつもりでも、伝え方ひとつでプレッシャーや誤解を生むことがあるため、注意が必要である。
たとえば、「みんなはできてるよ」「普通はこうするよ」といった言い回しは、日本人同士なら励ましにもなるが、文化のちがう相手にはプレッシャーとなってしまう。
また、「ちゃんと理解してる?」「なんでできないの?」といった問いかけは、本人の努力を否定されたように感じさせることがある。
こうした言葉は、相手の自信を奪い、行動をさらに慎重にさせてしまう。
態度についても同じで、「何も言わずに様子を見る」「目を合わせない」「表情を変えない」などの行動は、相手にとって“関心がない”や“歓迎されていない”という印象を与える。
文化のちがいを意識せず、自分の感覚だけで接してしまうと、信頼関係を築くどころか、壁を作ってしまうことになる。
まずは、「相手にどう届いているか」を想像しながら言葉を選ぶことが大切である。
少しの気づかいが、コミュニケーションの温度を大きく変える。
なぜ“魔法の言葉”が効果的なのか?その根拠と背景
異文化マネジメント理論と実践
外国人部下との関係を築くうえで、“魔法の言葉”が効果的である理由は、異文化マネジメント理論にしっかりと裏づけされている。
文化のちがう人同士が協力して働くためには、「ちがいを前提にした関わり方」が必要とされるからである。
たとえば、オランダの研究者ホフステードによる文化比較理論では、日本は「集団主義」や「曖昧さへの耐性の低さ」が強いとされている一方、欧米諸国では「個人主義」や「はっきりものを言う」ことが重視される傾向がある。
このような価値観のちがいをふまえないまま接すると、同じ言葉でも受けとめ方がちがってしまう。
だからこそ、「ちゃんと伝えたつもり」ではなく、「どう伝わったか」に気を配ることが重要である。
相手の文化背景や価値観を尊重した言葉がけは、安心感を生み、信頼の土台になる。
異文化マネジメントの実践とは、“正しさ”ではなく“理解しようとする姿勢”を持ちつづけることである。
モチベーション理論に見る「承認欲求」の重要性
部下のモチベーションを高めるうえで、“認めてもらえる”という感覚はとても大きな意味を持つ。
これは心理学の「マズローの欲求5段階説」にも見られる「承認欲求」と深く関係している。
マズローは、人は基本的な欲求が満たされると、次に「周囲から認められたい」「自分の価値を感じたい」という気持ちを強く持つと説いている。
たとえば、外国人部下が異動直後に戸惑いながら仕事をしている中で、小さな努力や工夫を見て「よくやってくれてるね」と声をかけるだけでも、その欲求は満たされやすくなる。
逆に、「やって当たり前」と思われるような空気がつづくと、やる気は目に見えないうちにしぼんでしまう。
だからこそ、“魔法の言葉”は、相手の心に自信と安心を与える。
承認の言葉は、ただの励ましではなく、モチベーションの根っこに働きかける行動そのものである。
海外でも実践されているリーダーの声かけ例
“魔法の言葉”は、日本だけでなく、海外の企業でもリーダーたちの間で実践されている。
文化のちがいにかかわらず、部下との信頼関係を築くためには、ことばを通じた承認と尊重がカギになるからである。
アメリカのチームマネジメントの事例
アメリカの企業では、「あなたの視点は価値がある」「アイデアに感謝している」といった、直接的で前向きな声かけがよく使われている。
たとえば、チーム会議で意見を出した部下に対して、「あなたの考えがチームに新しい視点を与えてくれた」と伝えることで、自信と参加意欲を高めている。
また、「自分が思っていた以上に評価されていた」と感じた部下は、自然と行動に前向きさがあらわれるようになる。
こうした言葉の力は、文化をこえて働くことが多く、組織内の心理的安全性にもつながっている。
ヨーロッパ企業の多文化対応術
ヨーロッパの多国籍企業では、「文化のちがいは強みである」という前提でコミュニケーションが設計されている。
たとえば、ドイツやスウェーデンの企業では、会議の場で「この点は他の文化ではどう見える?」とあえて意見を求めるスタイルが取られている。
このように、文化的ちがいを尊重する姿勢をことばにすることが、互いの信頼関係を深める要素として機能している。
「違うこと」が評価され、「共有されること」が歓迎される文化は、多様な部下のモチベーションを自然に引き出している。
日本でも、このような姿勢を取り入れることで、外国人部下が安心して力を出せる空気をつくることができる。
実際に効果があった“魔法の言葉”活用事例
IT企業での外国人エンジニア支援例
外国人部下のやる気と実力を引き出した例として、ある国内IT企業の取り組みが参考になる。
ここでは「あなたの考え方を、チームにも共有してもらえるとうれしい」といった声かけが、外国人エンジニアの自信を大きく変えた。
この企業では、インド出身の若手エンジニアが、入社直後はチーム会議でも発言が少なく、「期待ほど動いていない」と感じる上司が多かった。
だが、あるマネージャーが「日本語じゃなくてもいいから、あなたの専門的な視点を聞かせて」と、英語で声をかけたことで、本人の表情が明らかに変わったという。
その後はSlackで積極的にアイデアを発信し、プロジェクトの方向性にも影響を与えるようになった。
この例が示すのは、「自分の考えを求められている」という実感が、行動を変えるきっかけになるということである。
環境を整えるだけでなく、ことばで“居場所”をつくることが大きな意味を持つ。
製造業におけるチームワーク向上のケース
製造現場でも、“魔法の言葉”によってチームの空気が変わった事例がある。
ある中堅の製造業では、フィリピン出身の作業員に対し、「あなたがいてくれて本当に安心するよ」と日々伝えることを意識したところ、現場の雰囲気が明るくなった。
当初は、黙々と作業する姿を「無口でやる気がない」と受けとられていたが、実際は「間違えたくない」「質問が失礼に聞こえないか不安」と感じていたという。
そんな中、リーダーが毎朝の朝礼で「あなたのていねいな作業を、みんなが頼りにしてる」と伝えたことで、本人の表情がやわらぎ、作業後のコミュニケーションも増えていった。
チームメンバーの理解も深まり、自然と「ありがとう」「助かってるよ」という声が現場に増えていった。
こうした言葉の循環が、チームワークそのものを底上げする力になる。
実際の声:「今までで一番嬉しかった言葉」
“魔法の言葉”が心に届いた瞬間を、当事者の声から知ることができる。
ある日本の外資系企業で働くフランス人スタッフが「今までで一番うれしかった言葉は?」という問いに、こう答えた。
「“あなたがこのチームにいてくれて、心からうれしい”って言われたとき、自分の存在そのものを認めてもらえた気がした」
それまでの職場では、仕事の成果については評価されても、人として受け入れられている感覚がなく、どこかよそ者のように感じていたという。
だがその一言で、自分の居場所ができたと実感し、仕事への向き合い方が前向きに変わったと語っている。
このように、「評価」ではなく「存在そのもの」を認める言葉が、深い安心感を与える。
業績やスキルに関係なく、誰もが必要とされたいと感じていることを、忘れてはならない。
モチベーションアップに成功した!部下の変化と組織の未来像
チーム全体の生産性向上
外国人部下のモチベーションが上がると、その変化は本人だけにとどまらず、チーム全体の生産性にまでよい影響をあたえる。
なぜなら、チームは「空気」によって動いている側面が大きく、ひとりの前向きな姿勢が、まわりの意識や行動にも波及するからである。
たとえば、ある中小企業の技術チームでは、ベトナム出身のエンジニアがリーダーからの声かけをきっかけに自信を取りもどし、提案や報連相が積極的になった。
それを見た若手社員たちも、「発言しても受けとめてもらえる」という安心感を得て、全体の会話量やアイデア出しが増えたという。
業務のスピードや質が上がっただけでなく、会議中の無言の時間が減ったことで、ミスの発見や改善のサイクルも早まった。
これは、部下一人の変化がチームの「空気」を変えた好例である。
信頼が生まれる場所では、自然と生産性も高まりやすくなる。
外国人部下の主体性・創造性の向上
信頼と安心感を得た外国人部下は、指示を待つだけでなく、自ら動き、考え、提案するようになる。
この主体性の芽が育つと、創造的な発想や国際的な視点がチームにもたらされ、結果的に組織の柔軟性や競争力も強くなる。
たとえば、東京にあるスタートアップでは、アメリカ出身のマーケティング担当が最初は様子見だったものの、「あなたの経験をぜひ活かしてほしい」という一言で役割への向き合い方が変化。
翌週には、SNS戦略の改善案を自ら提案し、それが新規顧客の獲得数増加につながった。
こうした創造的な取り組みは、本人が「ここで自分が必要とされている」と感じたときに初めて出てくるものである。
部下の力を信じ、意見を求め、変化の余地をわたすことが、主体性の育成には欠かせない。
管理職自身のリーダーシップ進化
外国人部下との関わりを通じて、管理職自身のリーダーシップも深まり、より柔軟で共感力のあるスタイルへと進化していく。
なぜなら、文化や価値観のちがう相手に向き合う経験は、自分の固定観念を見なおすきっかけを与えてくれるからである。
たとえば、「伝えたつもりが伝わっていなかった」「理解したと思っていたが、実は誤解されていた」といった経験を積むことで、「どうすれば伝わるか」「どう感じているか」を自然と意識するようになる。
これは、どんな部下に対しても活きるマネジメント力であり、今後のキャリアにも大きなプラスとなる。
実際に、外国人部下を育成した経験をきっかけに、他部署との関係づくりや人材育成の方針を見直したという管理職も少なくない。
部下の成長とともに、自分自身も成長していくプロセスこそ、信頼されるリーダーへの道である。
変化の第一歩は「声かけ」から
「明日からできる一言」チェックリスト
部下との関係に悩んだとき、すぐに大きな変化を起こそうとしなくても大丈夫である。
ほんの一言から始めることで、少しずつ信頼と安心が育っていく。
たとえば、今日の仕事ぶりに「ありがとう」と伝える、ちょっとした工夫に「そのやり方、いいね」と気づく、それだけでも相手の表情は変わる。
もし言葉が見つからないときは、「どう思う?」「困ってない?」と問いかけるだけでも、相手の心に寄り添える。
以下のような一言を、ぜひ明日から使ってみてほしい。
- 「いてくれて助かってるよ」
- 「あなたの意見、聞いてみたい」
- 「そういう視点、チームにとって大切だと思う」
- 「ありがとう、その姿勢すごく伝わってるよ」
大切なのは、完ぺきな言葉を探すことではなく、「気にかけているよ」という気持ちを、ことばにすること。
小さな声かけの積み重ねが、大きな信頼につながっていく。
お悩みはお気軽にご相談ください(問い合わせ導線)
ここまで記事を読んでくださったあなたは、すでに部下を理解しようとする一歩を踏み出しています。
でも、実際の現場では「どう声をかければいいか分からない」「本当にこれでいいのか不安」と感じることもあるかもしれません。
そんなときは、一人で悩まず、ぜひご相談ください。
あなたの職場環境や部下の状況にあわせた具体的なアドバイスを、一緒に考えるお手伝いをさせていただきます。
どんな小さな疑問や不安でもかまいません。
このブログには、同じように悩みながらも前に進もうとしている管理職の方が多く訪れています。
フォームまたはコメント欄から、お気軽にメッセージをお寄せください。
あなたと部下の未来が、今より少しでも明るくなるよう、心から応援しています。
共感・応援メッセージを添えて
最後に、このページにたどりついたあなたに、心からのエールをお伝えしたいと思います。
異動してきた外国人部下との関わりは、簡単ではないこともあるかもしれません。
でも、あなたが感じている「どうにかしてあげたい」という思いは、すでに部下にとっての安心の種になっています。
ことばひとつで人の心が動き、空気が変わることがあります。
その力は、特別な技術や知識がなくても、だれにでも持てるものです。
あなたの声かけが、部下の目を輝かせ、チームの空気をあたたかく変えていく日が、きっとすぐそこにあります。
一歩ずつ、ていねいに。
このブログは、そんなあなたのそばに、これからも寄り添っていきたいと思っています。