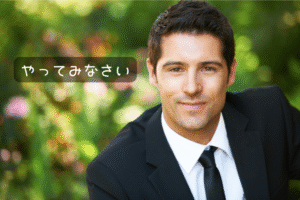【部下が安心する上司の条件】信頼される上司に共通する習慣とは?

あなたは本当に「良い上司」?部下の本音を知ろう
部下のためにと日々がんばっているあなたは、すでに「良い上司」への道を歩んでいます。
ただ、部下の心のなかにある本音は、目に見える行動や言葉だけではなかなか見えてきません。
笑顔の裏に「話しづらいな…」という気持ちがあったり、報告が少ないのは「相談しにくい雰囲気」だからかもしれません。
部下は、上司のあなたに気をつかい、本音を言わずに我慢していることがよくあります。
そこでこの章では、部下が実は心の中で思っている「上司への気持ち」や「不満のタネ」、そしてその裏にある“本当の望み”を、そっとひもといていきます。
大切なのは、「本音を言わないのは悪いこと」ではなく、「言えない環境になっているかもしれない」と気づくこと。
その気づきが、部下との信頼関係を深める大きな一歩になります。
仕事ぶりでは見抜けない!部下の本音とは
表面上、何の問題もなく見える部下でも、心の中ではさまざまな感情を抱えていることがあります。
ていねいな報連相や期限どおりの仕事だけでは、その奥にある気持ちを読み取ることはむずかしいです。
なぜなら、人は「この上司には言っても変わらない」と感じていると、あえて不満を言わず、黙って耐えることがあるからです。
たとえば、笑顔で「わかりました」と答えていても、実は心の中で「また急に言われた…」と感じているかもしれません。
このような本音に気づくには、部下のふだんの表情や話し方の変化に気をつけることが大切です。
ちょっとした言葉のトーン、視線、間の取り方など、仕事ぶりでは見えない「小さなサイン」が、部下の心の状態を教えてくれます。
だからこそ、評価や成績だけに目を向けるのではなく、「どんな気持ちで働いているか」にも意識を向けていきましょう。
部下が言わない「上司への不満」ランキング
多くの部下は、上司への不満をあまり口にしません。
でも、聞かれてもいないから言わないだけで、「ほんとうはこうしてほしい」という気持ちは、しっかりと持っています。
たとえば、よくある不満には
- 「忙しそうで声をかけづらい」
- 「話をちゃんと聞いてくれない」
- 「すぐに感情的になる」
などがあります。
これらは本人にとって大きなストレスになっているのに、なかなか上司には伝えられません。
さらに、「そのやり方、もう古いです」と思っていても、言ったら角が立つと感じて黙っていることもあります。
だから、部下の不満が表に出ないからといって、「不満がない」と思い込まないことが大切です。
不満が出てこないのは、信頼されていないわけではありません。
むしろ、「がっかりされたくない」「怒られたくない」と思って、あえて沈黙している優しい部下が多いのです。
「察してほしい」部下の気持ちとは
部下の多くは、はっきり言葉にしなくても
- 「気づいてほしい」
- 「わかってほしい」
と思っていることがあります。
これは、仕事への熱意や不満をうまく言葉にできない、あるいは言いづらい環境があるからです。
たとえば、「がんばっているのに何も言われない」と感じる部下は、「一言ほめてもらえたら、もっとやる気が出るのに」と思っているかもしれません。
また、「最近、元気がないな」と気づいてもらえるだけで、「見てくれている」と安心できる人もいます。
この「察してほしい」気持ちは、決してわがままではありません。
部下なりに、空気を読んだり気をつかったりしながら、毎日をがんばっている証なのです。
上司が少しだけ目を配り、声をかけることで、部下は「わかってもらえた」と感じて、より深い信頼関係が生まれます。
無意識にやっている“地雷”行動とは
自分ではふつうだと思っている行動が、実は部下の心をチクっと刺してしまっていることがあります。
たとえば、「それ、前にも言ったよね?」という一言。
意図は確認でも、部下にとっては責められたように聞こえることがあります。
また、相手の話を途中でさえぎったり、スマホを見ながら話を聞くのも、無意識のうちに「ちゃんと話を聞いてくれない人」という印象を与えてしまいます。
こうした“地雷”行動は、わずかな習慣の積み重ねです。
でも逆に言えば、意識して直すことができれば、信頼を築くチャンスにもなります。
まずは自分のふるまいを見直すことから始めてみましょう。
それだけで、部下の反応がやわらかくなることに気づくはずです。
表情・態度のサインに注目しよう
言葉で何も言わなくても、部下の表情や態度はたくさんのことを伝えています。
たとえば、いつも明るかった人が最近あまり目を合わせない、笑顔が少ない、返事が短い。そういった小さな変化は、「実は今、気持ちが沈んでいる」サインかもしれません。
このようなサインを見逃さないためには、日ごろから部下の様子にアンテナを張っておくことが大切です。
そして、変化に気づいたら、「最近なにかあった?」とやさしく声をかけるだけで、部下の安心感につながります。
部下にとって、「見てもらえている」「気にかけてもらえている」という感覚は、仕事のモチベーションにも直結します。
少しの気づきと、ちょっとした声がけが、部下との信頼の芽を育ててくれます。
良い上司に共通する5つの条件
部下との関係づくりに悩んだとき、「あの人はなぜ、うまくやれているのだろう?」と気になることがあるかもしれません。
実は、信頼される上司にはいくつかの共通点があります。
それは特別な才能ではなく、少しの意識と行動の積み重ねによるものです。
ここでは、成長中のあなたにもすぐに取り入れられる「5つの条件」をご紹介します。
どれも難しいことではなく、部下を思いやる気持ちがあれば少しずつ実践できる内容です。
今の自分を振り返りながら、できるところから始めてみましょう。
条件① 信頼される言動と行動
上司として一番大切なのは、「この人になら任せられる」と思ってもらえることです。
信頼されるためには、言葉と行動が一致していることが必要です。
つまり、
- 「言ったことを守る」
- 「一貫した態度で接する」
という小さな誠実さの積み重ねが、信頼の土台になります。
たとえば、部下に「困ったときは相談してね」と言ったのなら、実際に相談されたときに、手を止めてちゃんと向き合う姿勢が求められます。
逆に、「忙しいから後にして」と突き放してしまえば、その一言が信頼を遠ざける原因になってしまいます。
信頼される上司は、背伸びせず、できることをきちんとやる人です。
派手なパフォーマンスよりも、地道な対応が、部下の心を動かします。
条件② フィードバックの上手さ
良い上司は、部下の成長を支える「フィードバック」がとても上手です。
ただし、これは一方的に「こうしなさい」と伝えることではありません。
上手なフィードバックとは、
- 「何が良かったか」
- 「どこを直すともっと良くなるか」
を、具体的に伝えることです。
たとえば、「報告が早くて助かったよ。
次は内容をもう少し整理して書けると、もっと伝わりやすくなるね」というように、前向きな視点で伝えると、部下も素直に受け取りやすくなります。
頭ごなしに否定するのではなく、認める部分と改善点をバランスよく伝える。
それだけで、部下のやる気も自信も大きく変わっていきます。
条件③ 聴く力=傾聴スキル
「ちゃんと聴いてくれる上司」は、それだけで部下から安心されます。
ここで大切なのは、「聞く」ではなく「聴く」こと。
つまり、ただ話を受け流すのではなく、相手の気持ちや背景まで想像しながら耳を傾ける姿勢が大切です。
部下が話すときに、途中で口をはさまず、うなずきながら「そうなんだね」と共感を見せる。
これだけでも、部下は「わかってくれようとしている」と感じてくれます。
また、意見が出てこないときには「感じたことを、そのままだして」と問いかけて、沈黙を恐れずに待つことも効果的です。
上司がきちんと聴いてくれるとわかれば、部下は少しずつ本音を話してくれるようになります。
条件④ 公平な評価と対応
「えこひいきしている」と感じさせる上司には、部下も心を開きません。
良い上司は、誰に対しても同じ目線で接し、それぞれの努力や成果をきちんと見ようとします。
公平であるというのは、ただ同じように扱うことではありません。
たとえば、経験の浅い部下とベテランの部下では、求める水準がちがって当然です。
そのうえで、それぞれの成長に合わせた評価や声かけをしていくことが大切です。
特定の人ばかりを頼りにしたり、いつも同じ人をほめるといった行動は、周囲のモチベーションを下げてしまう原因になります。だからこそ、「ちゃんと見ているよ」と全員に伝わるようなふるまいを意識しましょう。
条件⑤ 感情を押し付けない冷静さ
上司も人間です。
イライラしたり、焦ったり、悩んだりすることもあります。
でも、感情をそのまま部下にぶつけてしまうと、相手は何も悪くなくても、心に傷を負ってしまいます。
良い上司は、どんなときも冷静に対応する力を持っています。
感情的になりそうなときは、まず深呼吸してから話すようにするなど、小さな工夫で落ち着いた対応ができるようになります。
また、自分の感情をコントロールするだけでなく、部下の感情にも配慮することが大切です。
「最近つかれてる?」と気づいて声をかけるだけで、部下の気持ちはずいぶん軽くなるものです。
上司の冷静さは、チーム全体に安心感を与えます。
だからこそ、感情を上手に整えることも、大切なスキルのひとつです。
パワハラと指導の違いとは?
「注意しただけなのに、パワハラって言われたらどうしよう」と不安に思う上司は少なくありません。
でも、パワハラと指導のちがいは、実はとてもシンプルです。
一番の違いは、「相手の成長を考えているかどうか」。
指導は、相手のミスや課題を改善して、次に生かせるように導く行動です。
一方、パワハラは、怒りや支配の気持ちから相手を傷つけるような言動です。
たとえば、「このやり方じゃダメだろ」とだけ言うのはパワハラになりがちですが、「ここをこうすれば、もっと良くなるよ」と伝えるのは建設的な指導になります。
そして、指導の場面でも大切なのは「伝え方」です。
大きな声や攻撃的な言葉では、どんなに正しい内容でも相手には届きません。
やさしい口調で、具体的な改善点を伝えることで、部下も前向きに受け止めることができます。
部下と信頼関係を築くコミュニケーション術
どんなに言葉を尽くしても、心の距離があると、伝えたいことは届きません。
部下との関係も同じです。
信頼は一朝一夕でつくれるものではなく、日々のコミュニケーションの積み重ねで育っていくものです。
ここでは、部下と自然に心を通わせるための、実践しやすい会話の工夫をご紹介します。
特別な技術や知識が必要なわけではありません。
小さな「声かけ」や「聞き方」を少し意識するだけで、関係は大きく変わっていきます。
雑談から始まる信頼づくり
多くの上司が「ちゃんと話を聞いているのに、なんだか距離を感じる」と悩んでいます。
実は、仕事の話だけで関係を築こうとすると、どうしても“必要な会話”になりがちで、心のやりとりが生まれにくいのです。
そこで役立つのが、何気ない雑談です。
たとえば、「美味しいラーメン屋さんを見つけたんだけど、この店知ってる?」「最近ハマっているものある?」といった、ちょっとした話題が心をゆるめるきっかけになります。
相手がリラックスできれば、本音も少しずつ出てきます。
雑談には、
- 「あなたに興味があります」
- 「あなたを気にかけています」
というメッセージが込められます。
無理に盛り上げなくてもかまいません。
続かなくても大丈夫です。
大切なのは、「話しかけてくれた」と感じてもらうことです。
週1回の「1on1ミーティング」のすすめ
部下と定期的にゆっくり話す時間があると、おたがいの理解が深まります。
そこでおすすめなのが、週に1回10〜15分の1on1ミーティングです。
内容は、仕事の進捗だけでなく、気になることや最近の気分についても話せると理想的です。
この時間は、「上司のため」ではなく、「部下のため」に使う時間です。
評価や指示を与える場ではなく、安心して本音を話せる場として設けましょう。
時間は短くてもかまいませんが、定期的に続けることが信頼づくりには重要です。
はじめのうちは、部下も警戒したり遠慮するかもしれません。
それでも、話すことがない日でも「どう?元気にしてる?」と問いかけるだけで、関係は少しずつ変わっていきます。
NGな質問・OKな質問とは?
部下との会話で「どう話しかけていいかわからない」と感じる方も多いでしょう。
とくに、本音を引き出したいときには、どんな質問をするかがとても大切です。
たとえば、「なんでできなかったの?」という問いは、責められていると感じやすく、部下の口を閉ざしてしまいます。
一方で、「どこがむずかしかった?」という聞き方をすれば、自然と状況を説明しやすくなります。
NGな質問は、YesかNoで終わってしまう質問や、相手を追い詰めるような聞き方です。
OKな質問は、相手の考えや感情を引き出せる、やわらかい問いかけです。
たとえば、「共感できる内容?」「ほかにやり方あったかも?」など、選択肢を広げるような聞き方が効果的です。
質問は、ただ答えを引き出すためだけでなく、「あなたの意見が大事だよ」と伝えるためのものでもあります。
本音を引き出す「沈黙」の使い方
会話の中で「沈黙」が続くと、気まずさを感じて、つい何か話さなきゃと思うかもしれません。
でも、沈黙には大事な意味があります。
それは、相手が考えている時間、気持ちを整理している時間です。
本音を引き出すには、この沈黙を「待つ勇気」が必要です。
たとえば、「プロジェクトは順調ですか?」と聞いて、すぐに答えが返ってこなくても、焦らずに目を見てうなずくだけでOKです。
相手は「話していいんだ」と感じ、少しずつ自分の言葉を探し始めます。
上司が沈黙を受け入れられると、部下も安心して、言いにくいことや迷っていることを話しやすくなります。
「沈黙=悪いこと」と思わず、「沈黙=信頼のサイン」ととらえて、ていねいに向き合ってみましょう。
Z世代・ミレニアル世代の部下への対応の違い
いまの職場では、20代前半のZ世代から30代のミレニアル世代まで、さまざまな価値観をもった部下が一緒に働いています。
それぞれに合った対応をすることで、コミュニケーションがスムーズになります。
Z世代は、生まれたときからインターネットが身近にあり、「自分らしさ」や「納得感」を大切にする傾向があります。
この世代には、上から指示するのではなく、意味や理由をきちんと説明してから任せるスタイルが効果的です。
一方、ミレニアル世代は、努力やスキルアップへの意識が高く、「成長実感」や「評価の透明性」を求める傾向があります。
この世代には、ていねいなフィードバックや、自分の努力がどう評価されたかを明確に伝えることが信頼関係を深めます。
同じ「若手」といっても、感じ方や求めるものはちがいます。
だからこそ、一人ひとりに向き合い、その人に合ったかかわり方を心がけることが、信頼関係を築く近道になります。
上司の自己開示が、部下の安心感を生む
「上司は、強くて完璧でなければいけない」──そう思って、自分の弱さや迷いを見せられないと感じることはありませんか。
でも実は、部下は「完璧な人」よりも、「人間らしさのある上司」に親しみと安心を感じます。
自己開示とは、自分の考えや気持ち、過去の体験などを、適切なタイミングで相手に伝えることです。
この少しの「ひらき」が、部下との信頼関係を深め、安心して働ける空気をつくっていきます。
ここでは、どんな自己開示が効果的なのか、具体的に見ていきましょう。
弱みを見せられる上司が強い理由
上司が「弱み」を見せるのは、部下にとって決してマイナスではありません。
むしろ、「この人にも悩むことがあるんだ」と感じることで、距離がぐっと近くなります。
たとえば、「自分も最初はミスばかりでね」と過去の不安や苦労を話すことで、部下は「自分だけじゃない」と安心できます。
これは、部下に同じ失敗をさせないようにという配慮ではなく、「あなたの気持ちがわかるよ」という、共感の姿勢の表れです。
強さとは、すべてを完璧にこなすことではありません。
大切なのは、自分の弱さを認め、それを伝える勇気を持つこと。
その姿に、部下は「自分もがんばろう」と前向きな気持ちを抱きます。
失敗談を共有するメリット
上司として、過去の失敗を話すことにためらいを感じるかもしれません。
でも、失敗談こそが、部下にとって「勇気」と「学び」の源になります。
たとえば、「昔、こんなふうにお客様を怒らせてしまったことがあって…」というエピソードを話すと、部下は「え、そんなこともあったんだ」と驚きながらも、自然と話に引き込まれます。
そして、「失敗しても、ちゃんと乗り越えられるんだ」と、自分の未来に希望を持てるようになります。
また、失敗をどう振り返り、どう次につなげたのかを話すことで、部下の中にも「失敗を前向きにとらえる視点」が育ちます。
これは、ただ注意するよりもずっと効果的な“教え”になります。
共有された失敗談は、ただの過去話ではなく、部下の成長を支える大切な教材になるのです。
「感情の共有」が信頼を深める
上司が「どう感じたか」を伝えることも、部下との信頼関係を深めるうえでとても大切です。
たとえば、「あのとき、うれしかったよ」といった、素直な感情の言葉は、部下にとって心に残る一言になります。
感情を共有することは、
- 「あなたのことをちゃんと見ているよ」
- 「あなたと一緒に感じているよ」
というメッセージになります。
これは、無理にポジティブなことを言う必要はなく、「自分もあの場面は戸惑ったな」など、正直な気持ちを言葉にするだけでも十分です。
部下もまた、感情を抱きながら働いています。
その感情をわかってくれる上司の存在は、大きな支えになります。
「自分の気持ちをわかってくれる上司」がいる職場は、安心して本音を出せる場所になります。
そして、その安心感が、チーム全体の信頼と団結を育てていくのです。
部下が辞めない職場づくりのヒント
- 「最近、若手がすぐに辞めてしまう」
- 「何が不満だったのかわからない」
そんな悩みを抱えている管理職の方は少なくありません。
ですが、部下が離れていく理由は、大きな事件や失敗ではなく、日々のちょっとした行き違いや「わかってもらえない」と感じた積み重ねであることが多いのです。
ここでは、部下が安心して長く働ける職場づくりのヒントをご紹介します。
「やめたくない」と思ってもらえる環境は、特別な制度ではなく、ふだんの声かけや態度から生まれます。
小さな気づきが、大きな信頼に変わるのです。
「心理的安全性」が高い職場とは?
心理的安全性とは、
- 「ここでは自分らしくいても大丈夫」
- 「間違えても受け入れてもらえる」
と感じられる空気のことです。
これは、職場の人間関係の中で、部下がもっとも大切にしている安心感のひとつです。
たとえば、会議で発言したあとに否定されず、きちんと耳を傾けてもらえたり、ミスをしても怒られずに「一緒に見直そう」と声をかけてもらえたとき。
そうした体験が、「ここなら大丈夫」と思える信頼の土台をつくります。
反対に、いつもピリピリしていて質問しづらい空気のある職場では、部下は自分を守るために、どんどん心を閉ざしてしまいます。
上司がまず「大丈夫だよ」と受け入れる姿勢を見せることで、職場全体にやさしい空気が広がり、部下の定着率にもつながっていきます。
部下が長く働きたくなる上司の特徴
部下が「この人のもとで働きたい」と思う上司には、共通した特徴があります。
それは、言葉や態度で「自分を大切にしてくれている」と感じさせてくれる存在であることです。
たとえば、忙しい中でも「最近どう?」と声をかけてくれる、努力を見てくれている、相談するとしっかり向き合ってくれる──そんな日常の行動こそが、部下にとっての「離れがたい理由」になります。
また、自分の仕事がチームや会社の中でどう役に立っているのかを伝えてくれる上司は、部下の働く意味ややりがいを引き出してくれます。
「成長できる」「見てもらえている」と実感できる環境こそが、部下にとっての安心感と信頼を育て、長く働きたい気持ちへとつながっていきます。
モチベーションが下がる職場の特徴
どんなに能力がある部下でも、環境によってやる気をなくしてしまうことがあります。
モチベーションが下がる職場には、いくつかの共通点があります。
たとえば、
- 「がんばっても認められない」
- 「何をしても反応がない」
- 「改善の提案が無視される」
といった、部下の存在が軽んじられているように感じる場面です。
こうした空気が続くと、「いても意味がないのかも」と感じて、気づかないうちに心が離れていきます。
また、指示ばかりで裁量が与えられない、失敗を責められる雰囲気が強いなど、「自分らしく動けない職場」も、部下のやる気を奪う原因になります。
だからこそ、「ここで働いていていいんだ」と思える言葉や態度を、ふだんから意識することが大切です。
ちょっとした一言で、部下の心は前向きになれるのです。
「頑張りが報われる環境」づくりとは?
どれだけ努力しても、何も変わらないと感じたら、人はやる気を失ってしまいます。
だからこそ、「頑張った分だけ、ちゃんと報われる」と思える環境をつくることが、部下の定着には欠かせません。
たとえば、小さな成功でも「よくやったね」と言葉で伝える、努力している姿を見逃さずに「見てるよ」と声をかける。
そうした日々のリアクションが、部下にとってのごほうびになります。
また、評価や昇格の理由をていねいに説明することで、「ちゃんと見てもらえている」と実感できます。
透明性のあるルールと、感情に左右されない判断も、部下の信頼につながります。
上司の役目は、ただ結果を見るだけではなく、そこまでのプロセスに目を向けること。
そして、努力がちゃんと報われる場所をつくることです。
その積み重ねが、部下の「ここで働き続けたい」という気持ちを育てていきます。
良い上司への第一歩は「気づき」から始まる
- 「もっと良い上司になりたい」
- 「信頼される存在になりたい」
そう思ったとき、大切なのは完璧を目指すことではありません。
ほんの少し立ち止まり、自分を見つめ直す「気づき」から、すべては始まります。
良い上司になるために必要なのは、特別なスキルや資格ではなく、自分のふるまいや考え方に対して、素直に向き合う姿勢です。
その気持ちが、行動を変え、信頼を育て、チームを前に進める原動力になります。
ここでは、その「気づき」を得るための3つのヒントをご紹介します。どれも今日から始められる、やさしい一歩です。
上司自身の「自己分析」が大切な理由
自己分析というと少し堅苦しく聞こえるかもしれませんが、ここで言うのは「自分のことを知る時間をもつ」という意味です。
ふだんの言動や態度をふり返ることで、部下にどう見られているか、自分がどうふるまっているかに気づくことができます。
たとえば、
- 「最近、部下とあまり話していないかも」
- 「伝え方が少しきつかったかもしれない」
など、小さな気づきが、行動の変化につながっていきます。
これは自分を責めるためではなく、「もっとよくなれるヒント」を見つけるためのものです。
自己分析は、自分の強みや、ついやってしまうクセに気づくチャンスでもあります。
一歩引いて自分を見つめることで、部下との関係性をより良くするヒントが見えてきます。
フィードバックをもらう勇気
上司という立場になると、なかなか自分へのフィードバックをもらえる機会が少なくなります。
でも、だからこそ、部下や周囲の声に耳を傾ける姿勢がとても大切です。
たとえば、
- 「何かやりづらいことある?」
- 「気になることがあったら教えてね」
と、自分からやさしく問いかけてみる。
それだけで、部下は「聞く耳をもってくれている」と感じ、少しずつ本音を伝えてくれるようになります。
もちろん、すべてを受け入れる必要はありません。
でも、たとえ厳しい内容であっても、「教えてくれてありがとう」と受け止める姿勢が、部下の信頼をぐっと深めてくれます。
フィードバックは、上司にとっても「育つきっかけ」です。
その一言が、自分では気づけなかった視点を与えてくれます。
小さな変化が信頼を生む
「上司として完璧にならなければ」と思うと、どうしても行動にブレーキがかかってしまいます。
でも、信頼関係は、一度の大きな変化ではなく、毎日のちょっとした行動から生まれます。
たとえば、朝「おはよう」と笑顔であいさつするだけでも、職場の空気は少しやわらかくなります。
ふだん言えなかった「ありがとう」を伝えてみる、部下の努力を見逃さずにほめてみる。
そんな小さな一歩が、部下の心に残るきっかけになります。
「変わろう」とする姿を見せること自体が、部下にとってはとても大きな意味を持ちます。
完璧でなくても、「変わろうとしてくれている」その気持ちが伝われば、信頼は少しずつ積み重なっていきます。
悩めるあなたへ、応援メッセージ
上司という立場は、見えないプレッシャーや孤独を感じやすいものです。
部下の前ではしっかりしていたい、でも本当は迷いながら日々を過ごしている。
そんなあなたの姿は、決して弱さではありません。
これまでの記事を読んで、「自分も変われるかもしれない」と思えたなら、それはすでに素晴らしい第一歩です。
ここからは、少しずつ、あなたらしい歩みを進めていきましょう。
あなたの悩みは、成長の証です
「自分は良い上司だろうか」「もっと良くなりたい」──そんなふうに悩むのは、それだけ部下を大切に思っている証です。
何も感じなければ、迷いすら生まれません。
つまり、その悩みは「成長しようとしている自分」と向き合っている証拠です。
そして、部下との関係に心を寄せているあなたは、すでに“良い上司”の一歩を踏み出しています。
完璧でなくていい。
時には失敗してもいい。
そのすべてを通して、上司としての人間味が部下の安心感になっていきます。
部下も上司も、共に育つ関係へ
上司と部下の関係は、「教える人」と「教わる人」ではなく、「共に学び、共に育つ関係」です。
上司が学ぶ姿を見せることで、部下も自分の成長を信じられるようになります。
ときには部下の言葉にハッとさせられることもあるでしょう。
そんな経験こそが、あなたの上司としての幅を広げてくれます。
一方通行の関係ではなく、思いやりのキャッチボールができる関係を目指していきましょう。
その積み重ねが、あなたのチームを、あたたかく信頼に満ちた場所に変えていきます。
感想・ご相談はこちらからどうぞ
ここまでお読みいただき、本当にありがとうございました。
もし、記事を読んで「気づきがあった」「心が少し軽くなった」と思えたなら、それはあなたがすでに変わりはじめている証です。
気になること、もっと聞いてみたいこと、「うちの職場ではこうだけどどうしたら?」といった具体的なご相談も、ぜひお気軽にお寄せください。
あなたと、あなたの部下が、笑顔で仕事に向き合えるようになるために。
わたしたちは、いつでもあなたのそばで応援しています。